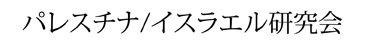2021年度以前の研究会はこちらから
2025年度の研究会
「パレスチナ/イスラエル紛争の変容②」 2025年度第2回研究会
概要
テーマ パレスチナ/イスラエル紛争の捉え方
日時 2025年8月1日(金)15:00-19:00
場所 東京大学駒場キャンパス18号館4階セミナールーム2,オンライン会議室
15:00~16:20 今野泰三(AA研共同研究員・中京大学)
16:30~17:50 役重善洋(AA研共同研究員・大阪経済法科大学)
18:00~ 研究メンバー会議(事務連絡等)
会場での参加(配付資料あり)はこちら
Zoomによるオンライン参加登録はこちら
主催:東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所共同利用・共同研究課題「パレスチナ/イスラエル紛争の変容②」(2025~27年度)
パレスチナ/イスラエル研究会
日時 2025年8月1日(金)15:00-19:00
場所 東京大学駒場キャンパス18号館4階セミナールーム2,オンライン会議室
15:00~16:20 今野泰三(AA研共同研究員・中京大学)
16:30~17:50 役重善洋(AA研共同研究員・大阪経済法科大学)
18:00~ 研究メンバー会議(事務連絡等)
会場での参加(配付資料あり)はこちら
Zoomによるオンライン参加登録はこちら
主催:東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所共同利用・共同研究課題「パレスチナ/イスラエル紛争の変容②」(2025~27年度)
パレスチナ/イスラエル研究会
報告
「パレスチナ/イスラエル紛争の変容②」 2025年度第1回研究会
概要
テーマ パレスチナ/イスラエル紛争の捉え方
日時 2025年6月20日(金)15:00-19:00
場所 東京大学駒場キャンパス18号館4階セミナールーム1,オンライン会議室
15:00~16:20 立山良司(AA研共同研究員・日本エネルギー経済研究所)
16:30~17:50 臼杵陽(AA研共同研究員・日本女子大学)
18:00~ 研究メンバー会議(事務連絡等)
会場での参加(配付資料あり)はこちら
Zoomによるオンライン参加登録はこちら
主催:東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所共同利用・共同研究課題「パレスチナ/イスラエル紛争の変容②」(2025~27年度)
パレスチナ/イスラエル研究会
日時 2025年6月20日(金)15:00-19:00
場所 東京大学駒場キャンパス18号館4階セミナールーム1,オンライン会議室
15:00~16:20 立山良司(AA研共同研究員・日本エネルギー経済研究所)
16:30~17:50 臼杵陽(AA研共同研究員・日本女子大学)
18:00~ 研究メンバー会議(事務連絡等)
会場での参加(配付資料あり)はこちら
Zoomによるオンライン参加登録はこちら
主催:東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所共同利用・共同研究課題「パレスチナ/イスラエル紛争の変容②」(2025~27年度)
パレスチナ/イスラエル研究会
報告
立山良司氏の報告では、イスラエル政治の変遷、安全保障政策、中東和平プロセスに関する主要な論点について、自身のこれまでの関心事項を中心に整理しつつ、現状分析と課題が論じられた。冒頭では、労働党からリクードへの政権交代と、イスラエル社会の右傾化の要因が検討された。続いて、政軍関係や核戦略、イランに対する脅威認識を軸に、安全保障政策の分析を行った。米・イスラエル関係については、ユダヤ・ロビーやキリスト教福音派の影響に触れ、「特殊な関係」の実態を明らかにする意義を論じた。中東和平プロセスについては、オスロ合意の挫折を通じて、和平の非対称性とその失敗に関する研究の必要性を指摘した。また、平和構築に関しては、adaptive peacebuildingに基づくヘブロンでの成功事例と米国主導のSSRの失敗を考察した。質疑応答では、パレスチナ/イスラエルを取り巻く国際関係、イスラエル社会の分断、イランに対する脅威認識が主な論点となった。
臼杵陽氏の報告では、アラブ地域における民族・宗教・宗派の多様性を軸に、イスラエル/パレスチナ紛争の歴史的背景とパレスチナにおけるキリスト教の現状が論じられた。はじめに、A.ホーラーニーの経歴とその著作を紹介し、彼によるアラブ地域のマイノリティ分類を紹介した。1947年時点の議論を通じて、イスラエル建国によるマイノリティ分類の変化が示された。また、板垣雄三氏の中東構成論を踏まえ、中東における宗教・民族紛争が国境線と民族・宗派の居住分布の不一致に起因する点を論じた。さらに、パレスチナのキリスト教徒や各宗派、東方諸教会の歴史的背景、各宗派の典礼に関する解説を通じて、宗教的多様性の実態を明らかにした。質疑応答では、パレスチナ/イスラエルにおけるマイノリティの動向、ホーラーニーのマイノリティ区分および板垣雄三氏の構成論、パレスチナのキリスト教徒に関する議論が交わされた。
東佑太(東京外国語大学大学院博士前期課程)
臼杵陽氏の報告では、アラブ地域における民族・宗教・宗派の多様性を軸に、イスラエル/パレスチナ紛争の歴史的背景とパレスチナにおけるキリスト教の現状が論じられた。はじめに、A.ホーラーニーの経歴とその著作を紹介し、彼によるアラブ地域のマイノリティ分類を紹介した。1947年時点の議論を通じて、イスラエル建国によるマイノリティ分類の変化が示された。また、板垣雄三氏の中東構成論を踏まえ、中東における宗教・民族紛争が国境線と民族・宗派の居住分布の不一致に起因する点を論じた。さらに、パレスチナのキリスト教徒や各宗派、東方諸教会の歴史的背景、各宗派の典礼に関する解説を通じて、宗教的多様性の実態を明らかにした。質疑応答では、パレスチナ/イスラエルにおけるマイノリティの動向、ホーラーニーのマイノリティ区分および板垣雄三氏の構成論、パレスチナのキリスト教徒に関する議論が交わされた。
東佑太(東京外国語大学大学院博士前期課程)
2023年度の研究会
「パレスチナ/イスラエル紛争の変容」 2023年度第2回研究会(公開シンポジウム)
概要
テーマ オスロ合意から30年:最終的地位の現在と新たな課題
日時 2023年9月30日(土)10:00–18:00
場所 東京大学駒場キャンパスアドミニストレーション棟3階学際交流ホール,オンライン会議室
10:00~10:10 開会の辞
鈴木啓之(AA研共同研究員・東京大学)
10:10~12:00 第一パネル:オスロ合意とは何だったのか
錦田愛子(AA研共同研究員・慶應義塾大学)
江﨑智絵(AA研共同研究員・防衛大学校)
鶴見太郎(AA研共同研究員・東京大学)
浜中新吾(AA研共同研究員・龍谷大学)
コメンテーター:立山良司(AA研共同研究員)
司会:菅瀬晶子(AA研共同研究員・国立民族学博物館)
13:00~14:50 第二パネル:パレスチナ問題からの再考
今野泰三(AA研共同研究員・中京大学)
田浪亜央江(AA研共同研究員・広島市立大学)
高橋宗瑠(AA研共同研究員・大阪女学院大学)
金城美幸(AA研共同研究員・立命館大学)
コメンテーター:奈良本英佑(法政大学)
司会:南部真喜子(AA研共同研究員・東京外国語大学)
15:10~16:30 第三パネル:忘却された現実
児玉恵美(AA研共同研究員・東京外国語大学)
細田和江(AA研共同研究員・東京外国語大学)
役重善洋(AA研共同研究員・同志社大学)
山本健介(AA研共同研究員・静岡県立大学)
コメンテーター:臼杵陽(AA研共同研究員・日本女子大学)
司会:後藤絵美(AA研)
17:10~17:50 総合討論
17:50~18:00 閉会の辞
後藤絵美(AA研)
18:00- 研究メンバー会議(事務連絡等)
会場での参加(配付資料あり)はこちら
Zoomによるオンライン参加登録はこちら
主催:東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所共同利用・共同研究課題「パレスチナ/イスラエル紛争の変容」(2022~24年度)
パレスチナ/イスラエル研究会 東京大学中東地域研究センター(UTCMES)
日時 2023年9月30日(土)10:00–18:00
場所 東京大学駒場キャンパスアドミニストレーション棟3階学際交流ホール,オンライン会議室
10:00~10:10 開会の辞
鈴木啓之(AA研共同研究員・東京大学)
10:10~12:00 第一パネル:オスロ合意とは何だったのか
錦田愛子(AA研共同研究員・慶應義塾大学)
江﨑智絵(AA研共同研究員・防衛大学校)
鶴見太郎(AA研共同研究員・東京大学)
浜中新吾(AA研共同研究員・龍谷大学)
コメンテーター:立山良司(AA研共同研究員)
司会:菅瀬晶子(AA研共同研究員・国立民族学博物館)
13:00~14:50 第二パネル:パレスチナ問題からの再考
今野泰三(AA研共同研究員・中京大学)
田浪亜央江(AA研共同研究員・広島市立大学)
高橋宗瑠(AA研共同研究員・大阪女学院大学)
金城美幸(AA研共同研究員・立命館大学)
コメンテーター:奈良本英佑(法政大学)
司会:南部真喜子(AA研共同研究員・東京外国語大学)
15:10~16:30 第三パネル:忘却された現実
児玉恵美(AA研共同研究員・東京外国語大学)
細田和江(AA研共同研究員・東京外国語大学)
役重善洋(AA研共同研究員・同志社大学)
山本健介(AA研共同研究員・静岡県立大学)
コメンテーター:臼杵陽(AA研共同研究員・日本女子大学)
司会:後藤絵美(AA研)
17:10~17:50 総合討論
17:50~18:00 閉会の辞
後藤絵美(AA研)
18:00- 研究メンバー会議(事務連絡等)
会場での参加(配付資料あり)はこちら
Zoomによるオンライン参加登録はこちら
主催:東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所共同利用・共同研究課題「パレスチナ/イスラエル紛争の変容」(2022~24年度)
パレスチナ/イスラエル研究会 東京大学中東地域研究センター(UTCMES)
報告
開会の辞では、鈴木啓之氏(東京大学)が、1993年9月13日に調印されたオスロ合意から30年に至るまでの和平プロセスの動向を整理したうえで、イスラエル国家とパレスチナ解放機構の両当事者の握手から、なぜ和平が推進されなかったのかという問題提起がなされた。まず、オスロ合意で何が合意され、それがいかに崩壊に至ったのかというこれまでの和平プロセスの説明が行われた。その中で、オスロ合意には、交渉対象になっている物事の現状維持や現状の凍結を求める仕組みもなければ、合意に違反した場合の罰則の規定もなかったという問題点が挙げられた。厳しい状況が続く直近の10年間を振り返ってみると、オスロ合意が想定し、立脚してきた世界が徐々に崩れていき、より課題が鮮明になってきていることを受け、中東和平の現在地を照らし出すことが本シンポジウムのテーマであるとの趣旨説明がなされた。
第一パネルでは「オスロ合意とは何だったのか」をテーマに、菅瀬晶子氏(国立民族学博物館)の司会により、錦田愛子氏(慶応義塾大学)、江﨑智絵氏(防衛大学校)、鶴見太郎氏(東京大学)、浜中新吾氏(龍谷大学)が報告を行い、立山良司氏(防衛大学校名誉教授)がコメンテーターを務めた。
まず錦田氏の報告「オスロ合意の遺構とその変容」では、オスロ合意から30年が経過するなかで、「オスロ合意がもたらした大きな希望が、その崩壊により失われていった」との認識で正しいのかを再度考え直す必要があるとの問題提起がなされた。オスロ合意が作った枠組みはすべて頓挫したのではなく、一番大きなものとしては、パレスチナ自治政府が存続していることを示し、その要因を分析した。ガバナンス状態を示す世界銀行の指数では、イスラエルは優良国とされる一方で、パレスチナ自治政府のガバナンスの評価が極めて低いことを指摘し、この要因はパレスチナ自治政府のみに帰せられる問題ではなく、自治政府がイスラエルによる占領の組織化のために作られた組織なのであれば、そもそもパレスチナの独立や民主化が当初から想定されていなかった可能性があることを提起した。
江崎氏の報告「オスロ・プロセスをめぐる国際機構との関わり」は、国連とカルテット(アメリカ、ロシア、国連、EUの四者が結成したもの)を始めとする国際機構の一貫した二国家解決への姿勢、ならびにパレスチナ情勢の変化との関係から一体何が見えてくるのかを検討するものだった。報告では、パレスチナ情勢の変化の出発点を、2006年のハマースの立法評議会選挙における勝利に位置づけた。選挙結果を受け、カルテットやイスラエルはハマースに対して自治政府に参加する3条件を提示したが、受け入れられなかったために、カルテットはハマースの締め付けを強化した上で、ファタハへの支援を強化した。パレスチナの内政においても大きな変化が見られない中、その打開策としてアッバース大統領が2010年頃に掲げたのが、パレスチナの国連アプローチであり、パレスチナとしてイスラエルに圧力をかけうる手段として国連へのアプローチが重視されていたことが示された。結論として、国際機構は、オスロ合意の中核として存在している二国家解決策に明確な諸価値や規範意識をもち、それから逃れられない傾向が提起された。そのためにパレスチナ内部の分裂を助長するようなハマース対策が取られてきたことを指摘した。一方、ハマースとファタハによる内部分裂の長期化ゆえに、パレスチナ内部においても二国家解決策への実現可能性が減少しているという現実がある点を提起した。
鶴見氏の報告「シオニスト/イスラエルのアラブ観」は、イスラエルがこれまで「パレスチナ人」の存在を否定してきた中で、オスロ合意においては、イスラエルがパレスチナ人という固有の存在を認めたのは画期的であったが、それがどのような意味合いをもっていたのかを分析するものだった。シオニスト/イスラエルによるアラブ観の歴史的な変遷が提示されたことで、シオニストたちの思想的な立場の多様性が示唆された。結論として、オスロ合意においてシオニストやイスラエルは、落ち着き先が未定の残余のようなものとして認識していた人びとに改めて「パレスチナ人」という名前を与えたという以上のものではなかった点、さらに、シオニストが考えているところのユダヤ人と比肩する存在としてパレスチナ人を捉えるという意味合いは下火のまま消えてしまっている現状が指摘された。
浜中氏の報告「イスラエルの右傾化と和平への姿勢」は、計量政治分析に基づき、中東和平というイシューが、イスラエル人有権者の投票行動をどれほど規定しているのかを分析するものだった。イスラエル政治の右派と左派という政党のイデオロギーの焦点は占領地の扱いにある点を指摘しつつ、コンジョイント実験の結果として、ユダヤ系イスラエル人有権者の過半数は右派だと自己認識していること、パレスチナ自治政府との交渉再開は希望しない傾向が強いこと、ヨルダン川西岸地区の入植地拡大を主張する政党を支持する傾向が大きいことが明らかになった。したがって、イスラエルにおける国民世論の右傾化が、選挙における右派政党への支持となり、ネタニヤフ首相の最右翼政権が誕生したという構図が看取されることを提示した。
続いて、第二パネルでは、「パレスチナ問題からの再考」をテーマに、南部真喜子氏(東京外国語大学)の司会のもと、今野泰三氏(中京大学)、田浪亜央江氏(広島市立大学)、高橋宗瑠氏(大阪女学院大学)、金城美幸氏(立命館大学)が報告を行い、奈良本英佑氏(法政大学名誉教授)がコメンテーターを務めた。
今野氏の報告「ポスト・オスロ合意期における植民地主義研究の再評価と進展」は、植民地主義という枠組み、とくに入植者植民地主義の概念と分析枠組みの研究潮流を整理したうえで、パレスチナ/イスラエル研究におけるその意義と課題を論じるものだった。オスロ合意以前の研究において、PLOがシオニズムの植民地主義に対する祖国解放運動を展開するというパラダイムから、1970年代以降、パレスチナとイスラエル双方が祖国に対して正統な要求を持つとみなすパラダイムへと国際社会の圧力によって非自発的に移行したことにより、既存の研究潮流もこのパラダイム・シフトに引っ張られてきた傾向を指摘した。一方で、オスロ合意以後の研究では、パレスチナ人研究者の間で、植民地主義への再注目がなされていることを指摘する。今後の課題として、被植民者のパレスチナ人が帝国主義・植民地主義をいかに経験し、その中でいかに帝国主義・植民地主義・民族主義に反発または迎合しながら、生活・文化・社会関係を維持・喪失・変化させてきたのかを分析する必要性を提起した。
田浪氏の報告「オスロ以後のパレスチナの劇場/劇団」では、パレスチナの劇場/劇団が1970年代以降、武装闘争や大衆的実行行動と並ぶ/それに代わる抵抗の文化の拠点として発展してきた一方で、オスロ和平プロセスにおいては、平和構築モデルとしてイスラエルとパレスチナの信頼醸成装置という従来とは異なる役割への期待が生まれたことが示された。そのうえで、一つの公共空間へと発展してきた劇場をめぐる意義や目的の省察、再定義が求められるとの提起がなされた。劇場/劇団の機能として、イスラエル領内では抵抗というよりはアイデンティティ探求として置き換えられる点、劇場という場を作り維持することそれ自体が運動である点、イスラエル領内(ガリラヤ地方)出身者による被占領地との行き来を通して、オスロ後も両者の分断が進む中で、舞台を通して交流が可能となっている点を提示した。
高橋氏の報告「パレスチナと国連の取り組み」は、加盟国、主権国家の集まりである国連において、組織的にも資金的にも、大国の意向がパレスチナ問題に影響を与えてきた構造があることを考察するものだった。人道系の機関によるパレスチナ支援をめぐって、OHCHR(国連人権高等弁務官事務所)は、オスロ和平プロセスの下でラーマッラーに事務所を設置したものの、パレスチナ当局の支援を行うのみで、パレスチナ人の人権侵害の調査報告の任務がなかった点、他方で2008年のイスラエルによるガザ大規模侵攻の際には、人権理事会でイスラエル人の人権侵害の調査報告のみが指示された点から、人権活動の中立性が脅かされている側面が提起された。また、難民の人権と権利の「保護」が任務とされるUNHCRと異なり、パレスチナ難民を対象とするUNRWAには難民の「保護」が想定されておらず、実はパレスチナ難民支援への任務は狭く規定されているという問題点を指摘した。
金城氏の報告「パレスチナ難民の帰還権の『実践的』意味」は、エルサレムのリフター村を事例として、難民帰還権の意味付けが、パレスチナ難民の経験の中でいかに深化してきたのかを、村への帰還の実践から検討するものだった。離散先のヨルダン川西岸地区に住むリフター村出身者は、故郷であるリフター村とつながるために、①村民協会のネットワーク化、自費による村落史(7冊)の出版、②残存するリフターの家屋破壊に対する集団的な抗議活動、③ナクバ後の同村の跡地への帰還実践を行ってきたことが提示された。和平交渉では難民の帰還権が抽象的な大義として扱われてきた一方で、以上の考察からは、リフター村の村民たちが、難民帰還権の中身を具体的な将来像としてイメージし、それを限られた時間であれ経験として知覚している様子が示された。
最後に、第三パネルでは「忘却された現実」をテーマに、オスロ合意において周辺化された存在に光が当てられた。後藤絵美氏(東京外国語大学)の司会のもと、児玉恵美(東京外国語大学)、細田和江氏(東京外国語大学)、役重善洋氏(同志社大学)、山本健介氏(静岡県立大学)が報告を行い、臼杵陽氏(日本女子大学)がコメンテーターを務めた。
児玉の報告「レバノンのパレスチナ難民キャンプにおける暴力の持続性」では、レバノンのシャーティーラー難民キャンプ在住のパレスチナ人を対象に、オスロ合意に関する語りを確認したうえで、彼らがさらされてきた暴力がいかに持続してきたのかを検討することを目的とした。シャーティーラーを標的とする集団的暴力によって、同地は瓦礫の山の廃墟状態になり、住民の強制移動とその後の再建を経て、その場所に残存することができたのは、わずかな人々と、そこで殺害された死者の身体であった点、一方で、同キャンプの元住民が1982年の虐殺追悼日に国内外から同キャンプに身体を運んでいた様子が示された。
細田氏の報告「イスラエル文学におけるバイリンガリズムと翻訳」では、オスロ合意が調印された前後においてイスラエル社会の文学がいかに変容したのかを明らかにするものだった。イスラエル国家の根幹となる概念として「シオニズム」があり、イスラエルの主流の文化はヨーロッパ由来の世俗的なユダヤ・ヘブライ文化であった。その一方、オスロ合意以降、イスラエル文化の中に、オリエンタルなものとしてユダヤ・アラブ文化の受容、さらにはロシア語など多言語文化の受容が加速したという流れがあることを指摘した。文学に焦点を当てるならば、イスラエル文学は、ヨーロッパ系ユダヤ人によるヘブライ語の文学が中心であったが、ヨーロッパ出身でないユダヤ人とパレスチナ・アラブ人当事者によるヘブライ文学への「参入」が生じ、アラビア語での執筆が進んでいったことを提示した。以上の考察から、ユダヤ社会がアラブ文化を「イスラエル」のものとして受容しようとしている点が提示された。また、パレスチナ人社会の側にも、アラビア語の文学をヘブライ語に翻訳する動きがあることを指摘し、イスラエルの脱シオニズム化の試みがなされている点が示された。
役重氏の報告「考古学とイスラエルの政策」では、イスラエルがパレスチナ側の主権を制限し、侵害する足掛かりとして考古学を利用してきた歴史的過程が提起された。イスラエルの考古学を考える際に問題となるのは、イスラエルあるいはパレスチナ地域の歴史認識問題という側面、ならびに民族史観的なヘブライ語聖書解釈に基づき、占領政策として被占領地パレスチナの土地を「考古学」遺跡だと主張として、住民の追放と土地奪取を行っていることだと指摘した。こうした傾向は1990年代以降、学問性の低い商業的考古学と宗教シオニストを中核とする入植運動が癒着したことにより強化されたと述べた。一例として、パレスチナ人のシルワン村が「ダビデ王宮殿」の遺跡だと主張され、シルワン村住民の追放とユダヤ人入植、観光客誘致が展開された結果、イスラエルは「二重の成功」を収め、同政権にとって重要なモデルになったことが考察された。
山本氏の報告「オスロ合意と48年パレスチナ人」は、「48年パレスチナ人」と呼称されるイスラエル国内のパレスチナ人を対象とする。彼らにとってオスロ合意からの30年は何であったのかを、「イスラエルのイスラーム運動」のなかでも独自の道を歩んだ北部潮流に着目して全体像を浮き彫りにするものだった。同運動は、パレスチナ人意識を基盤としつつ、イスラエル国内における差別的待遇の撤廃と完全に平等な地位をめぐるローカルな闘争を展開してきた。「イスラーム運動」は1996年に国政参加とオスロ合意への立場をめぐり、北部潮流と南部潮流に分裂したが、本報告では、イスラエルの国政参加への拒絶を示す北部潮流に着目した。北部潮流が「自律社会」を掲げ、国政不参加や孤立主義を採っているのは、イスラエル政府への依存の拒否と自律性の希求であり、ユダヤ系市民や政府への不信感が強まる中でその活動が説得力を持っていること、ならびに、オスロ合意以後の閉塞化する生活空間に幻滅したパレスチナ人の受け皿になっている様子が示された。
後藤絵美氏による閉会の辞では、各発表者はオスロ合意が停滞している現在地にあって、どこに希望を見出せるのかを意識し、そこに思考を凝らしている様子がうかがえたこと、研究者としての我々の在り方が重要であることが提起され、本シンポジウムは終了した。
児玉恵美(東京外国語大学)
第一パネルでは「オスロ合意とは何だったのか」をテーマに、菅瀬晶子氏(国立民族学博物館)の司会により、錦田愛子氏(慶応義塾大学)、江﨑智絵氏(防衛大学校)、鶴見太郎氏(東京大学)、浜中新吾氏(龍谷大学)が報告を行い、立山良司氏(防衛大学校名誉教授)がコメンテーターを務めた。
まず錦田氏の報告「オスロ合意の遺構とその変容」では、オスロ合意から30年が経過するなかで、「オスロ合意がもたらした大きな希望が、その崩壊により失われていった」との認識で正しいのかを再度考え直す必要があるとの問題提起がなされた。オスロ合意が作った枠組みはすべて頓挫したのではなく、一番大きなものとしては、パレスチナ自治政府が存続していることを示し、その要因を分析した。ガバナンス状態を示す世界銀行の指数では、イスラエルは優良国とされる一方で、パレスチナ自治政府のガバナンスの評価が極めて低いことを指摘し、この要因はパレスチナ自治政府のみに帰せられる問題ではなく、自治政府がイスラエルによる占領の組織化のために作られた組織なのであれば、そもそもパレスチナの独立や民主化が当初から想定されていなかった可能性があることを提起した。
江崎氏の報告「オスロ・プロセスをめぐる国際機構との関わり」は、国連とカルテット(アメリカ、ロシア、国連、EUの四者が結成したもの)を始めとする国際機構の一貫した二国家解決への姿勢、ならびにパレスチナ情勢の変化との関係から一体何が見えてくるのかを検討するものだった。報告では、パレスチナ情勢の変化の出発点を、2006年のハマースの立法評議会選挙における勝利に位置づけた。選挙結果を受け、カルテットやイスラエルはハマースに対して自治政府に参加する3条件を提示したが、受け入れられなかったために、カルテットはハマースの締め付けを強化した上で、ファタハへの支援を強化した。パレスチナの内政においても大きな変化が見られない中、その打開策としてアッバース大統領が2010年頃に掲げたのが、パレスチナの国連アプローチであり、パレスチナとしてイスラエルに圧力をかけうる手段として国連へのアプローチが重視されていたことが示された。結論として、国際機構は、オスロ合意の中核として存在している二国家解決策に明確な諸価値や規範意識をもち、それから逃れられない傾向が提起された。そのためにパレスチナ内部の分裂を助長するようなハマース対策が取られてきたことを指摘した。一方、ハマースとファタハによる内部分裂の長期化ゆえに、パレスチナ内部においても二国家解決策への実現可能性が減少しているという現実がある点を提起した。
鶴見氏の報告「シオニスト/イスラエルのアラブ観」は、イスラエルがこれまで「パレスチナ人」の存在を否定してきた中で、オスロ合意においては、イスラエルがパレスチナ人という固有の存在を認めたのは画期的であったが、それがどのような意味合いをもっていたのかを分析するものだった。シオニスト/イスラエルによるアラブ観の歴史的な変遷が提示されたことで、シオニストたちの思想的な立場の多様性が示唆された。結論として、オスロ合意においてシオニストやイスラエルは、落ち着き先が未定の残余のようなものとして認識していた人びとに改めて「パレスチナ人」という名前を与えたという以上のものではなかった点、さらに、シオニストが考えているところのユダヤ人と比肩する存在としてパレスチナ人を捉えるという意味合いは下火のまま消えてしまっている現状が指摘された。
浜中氏の報告「イスラエルの右傾化と和平への姿勢」は、計量政治分析に基づき、中東和平というイシューが、イスラエル人有権者の投票行動をどれほど規定しているのかを分析するものだった。イスラエル政治の右派と左派という政党のイデオロギーの焦点は占領地の扱いにある点を指摘しつつ、コンジョイント実験の結果として、ユダヤ系イスラエル人有権者の過半数は右派だと自己認識していること、パレスチナ自治政府との交渉再開は希望しない傾向が強いこと、ヨルダン川西岸地区の入植地拡大を主張する政党を支持する傾向が大きいことが明らかになった。したがって、イスラエルにおける国民世論の右傾化が、選挙における右派政党への支持となり、ネタニヤフ首相の最右翼政権が誕生したという構図が看取されることを提示した。
続いて、第二パネルでは、「パレスチナ問題からの再考」をテーマに、南部真喜子氏(東京外国語大学)の司会のもと、今野泰三氏(中京大学)、田浪亜央江氏(広島市立大学)、高橋宗瑠氏(大阪女学院大学)、金城美幸氏(立命館大学)が報告を行い、奈良本英佑氏(法政大学名誉教授)がコメンテーターを務めた。
今野氏の報告「ポスト・オスロ合意期における植民地主義研究の再評価と進展」は、植民地主義という枠組み、とくに入植者植民地主義の概念と分析枠組みの研究潮流を整理したうえで、パレスチナ/イスラエル研究におけるその意義と課題を論じるものだった。オスロ合意以前の研究において、PLOがシオニズムの植民地主義に対する祖国解放運動を展開するというパラダイムから、1970年代以降、パレスチナとイスラエル双方が祖国に対して正統な要求を持つとみなすパラダイムへと国際社会の圧力によって非自発的に移行したことにより、既存の研究潮流もこのパラダイム・シフトに引っ張られてきた傾向を指摘した。一方で、オスロ合意以後の研究では、パレスチナ人研究者の間で、植民地主義への再注目がなされていることを指摘する。今後の課題として、被植民者のパレスチナ人が帝国主義・植民地主義をいかに経験し、その中でいかに帝国主義・植民地主義・民族主義に反発または迎合しながら、生活・文化・社会関係を維持・喪失・変化させてきたのかを分析する必要性を提起した。
田浪氏の報告「オスロ以後のパレスチナの劇場/劇団」では、パレスチナの劇場/劇団が1970年代以降、武装闘争や大衆的実行行動と並ぶ/それに代わる抵抗の文化の拠点として発展してきた一方で、オスロ和平プロセスにおいては、平和構築モデルとしてイスラエルとパレスチナの信頼醸成装置という従来とは異なる役割への期待が生まれたことが示された。そのうえで、一つの公共空間へと発展してきた劇場をめぐる意義や目的の省察、再定義が求められるとの提起がなされた。劇場/劇団の機能として、イスラエル領内では抵抗というよりはアイデンティティ探求として置き換えられる点、劇場という場を作り維持することそれ自体が運動である点、イスラエル領内(ガリラヤ地方)出身者による被占領地との行き来を通して、オスロ後も両者の分断が進む中で、舞台を通して交流が可能となっている点を提示した。
高橋氏の報告「パレスチナと国連の取り組み」は、加盟国、主権国家の集まりである国連において、組織的にも資金的にも、大国の意向がパレスチナ問題に影響を与えてきた構造があることを考察するものだった。人道系の機関によるパレスチナ支援をめぐって、OHCHR(国連人権高等弁務官事務所)は、オスロ和平プロセスの下でラーマッラーに事務所を設置したものの、パレスチナ当局の支援を行うのみで、パレスチナ人の人権侵害の調査報告の任務がなかった点、他方で2008年のイスラエルによるガザ大規模侵攻の際には、人権理事会でイスラエル人の人権侵害の調査報告のみが指示された点から、人権活動の中立性が脅かされている側面が提起された。また、難民の人権と権利の「保護」が任務とされるUNHCRと異なり、パレスチナ難民を対象とするUNRWAには難民の「保護」が想定されておらず、実はパレスチナ難民支援への任務は狭く規定されているという問題点を指摘した。
金城氏の報告「パレスチナ難民の帰還権の『実践的』意味」は、エルサレムのリフター村を事例として、難民帰還権の意味付けが、パレスチナ難民の経験の中でいかに深化してきたのかを、村への帰還の実践から検討するものだった。離散先のヨルダン川西岸地区に住むリフター村出身者は、故郷であるリフター村とつながるために、①村民協会のネットワーク化、自費による村落史(7冊)の出版、②残存するリフターの家屋破壊に対する集団的な抗議活動、③ナクバ後の同村の跡地への帰還実践を行ってきたことが提示された。和平交渉では難民の帰還権が抽象的な大義として扱われてきた一方で、以上の考察からは、リフター村の村民たちが、難民帰還権の中身を具体的な将来像としてイメージし、それを限られた時間であれ経験として知覚している様子が示された。
最後に、第三パネルでは「忘却された現実」をテーマに、オスロ合意において周辺化された存在に光が当てられた。後藤絵美氏(東京外国語大学)の司会のもと、児玉恵美(東京外国語大学)、細田和江氏(東京外国語大学)、役重善洋氏(同志社大学)、山本健介氏(静岡県立大学)が報告を行い、臼杵陽氏(日本女子大学)がコメンテーターを務めた。
児玉の報告「レバノンのパレスチナ難民キャンプにおける暴力の持続性」では、レバノンのシャーティーラー難民キャンプ在住のパレスチナ人を対象に、オスロ合意に関する語りを確認したうえで、彼らがさらされてきた暴力がいかに持続してきたのかを検討することを目的とした。シャーティーラーを標的とする集団的暴力によって、同地は瓦礫の山の廃墟状態になり、住民の強制移動とその後の再建を経て、その場所に残存することができたのは、わずかな人々と、そこで殺害された死者の身体であった点、一方で、同キャンプの元住民が1982年の虐殺追悼日に国内外から同キャンプに身体を運んでいた様子が示された。
細田氏の報告「イスラエル文学におけるバイリンガリズムと翻訳」では、オスロ合意が調印された前後においてイスラエル社会の文学がいかに変容したのかを明らかにするものだった。イスラエル国家の根幹となる概念として「シオニズム」があり、イスラエルの主流の文化はヨーロッパ由来の世俗的なユダヤ・ヘブライ文化であった。その一方、オスロ合意以降、イスラエル文化の中に、オリエンタルなものとしてユダヤ・アラブ文化の受容、さらにはロシア語など多言語文化の受容が加速したという流れがあることを指摘した。文学に焦点を当てるならば、イスラエル文学は、ヨーロッパ系ユダヤ人によるヘブライ語の文学が中心であったが、ヨーロッパ出身でないユダヤ人とパレスチナ・アラブ人当事者によるヘブライ文学への「参入」が生じ、アラビア語での執筆が進んでいったことを提示した。以上の考察から、ユダヤ社会がアラブ文化を「イスラエル」のものとして受容しようとしている点が提示された。また、パレスチナ人社会の側にも、アラビア語の文学をヘブライ語に翻訳する動きがあることを指摘し、イスラエルの脱シオニズム化の試みがなされている点が示された。
役重氏の報告「考古学とイスラエルの政策」では、イスラエルがパレスチナ側の主権を制限し、侵害する足掛かりとして考古学を利用してきた歴史的過程が提起された。イスラエルの考古学を考える際に問題となるのは、イスラエルあるいはパレスチナ地域の歴史認識問題という側面、ならびに民族史観的なヘブライ語聖書解釈に基づき、占領政策として被占領地パレスチナの土地を「考古学」遺跡だと主張として、住民の追放と土地奪取を行っていることだと指摘した。こうした傾向は1990年代以降、学問性の低い商業的考古学と宗教シオニストを中核とする入植運動が癒着したことにより強化されたと述べた。一例として、パレスチナ人のシルワン村が「ダビデ王宮殿」の遺跡だと主張され、シルワン村住民の追放とユダヤ人入植、観光客誘致が展開された結果、イスラエルは「二重の成功」を収め、同政権にとって重要なモデルになったことが考察された。
山本氏の報告「オスロ合意と48年パレスチナ人」は、「48年パレスチナ人」と呼称されるイスラエル国内のパレスチナ人を対象とする。彼らにとってオスロ合意からの30年は何であったのかを、「イスラエルのイスラーム運動」のなかでも独自の道を歩んだ北部潮流に着目して全体像を浮き彫りにするものだった。同運動は、パレスチナ人意識を基盤としつつ、イスラエル国内における差別的待遇の撤廃と完全に平等な地位をめぐるローカルな闘争を展開してきた。「イスラーム運動」は1996年に国政参加とオスロ合意への立場をめぐり、北部潮流と南部潮流に分裂したが、本報告では、イスラエルの国政参加への拒絶を示す北部潮流に着目した。北部潮流が「自律社会」を掲げ、国政不参加や孤立主義を採っているのは、イスラエル政府への依存の拒否と自律性の希求であり、ユダヤ系市民や政府への不信感が強まる中でその活動が説得力を持っていること、ならびに、オスロ合意以後の閉塞化する生活空間に幻滅したパレスチナ人の受け皿になっている様子が示された。
後藤絵美氏による閉会の辞では、各発表者はオスロ合意が停滞している現在地にあって、どこに希望を見出せるのかを意識し、そこに思考を凝らしている様子がうかがえたこと、研究者としての我々の在り方が重要であることが提起され、本シンポジウムは終了した。
児玉恵美(東京外国語大学)
「パレスチナ/イスラエル紛争の変容」 2023年度第1回研究会
概要
テーマ にじむ境界線
日時 2023年8月8日(火)15:00–19:00
場所 東京大学駒場キャンパス18号館4階セミナールーム,オンライン会議室
15:00-15:50 金城美幸(AA研共同研究員・立命館大学)
「パレスチナ難民の記憶の共有過程と難民帰還権:被占領地に暮らすリフター村出身者を中心に」
16:00-16:50 役重善洋(AA研共同研究員・同志社大学)
「被占領西岸地区およびエルサレムにおけるイスラエルの考古学発掘調査について」
17:00-17:40 全体討議
18:00- 研究メンバー会議(事務連絡等)
Zoomによるオンライン参加登録はこちら
会場での参加はこちら
主催:東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所共同利用・共同研究課題「パレスチナ/イスラエル紛争の変容」(2022~24年度)
パレスチナ/イスラエル研究会
日時 2023年8月8日(火)15:00–19:00
場所 東京大学駒場キャンパス18号館4階セミナールーム,オンライン会議室
15:00-15:50 金城美幸(AA研共同研究員・立命館大学)
「パレスチナ難民の記憶の共有過程と難民帰還権:被占領地に暮らすリフター村出身者を中心に」
16:00-16:50 役重善洋(AA研共同研究員・同志社大学)
「被占領西岸地区およびエルサレムにおけるイスラエルの考古学発掘調査について」
17:00-17:40 全体討議
18:00- 研究メンバー会議(事務連絡等)
Zoomによるオンライン参加登録はこちら
会場での参加はこちら
主催:東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所共同利用・共同研究課題「パレスチナ/イスラエル紛争の変容」(2022~24年度)
パレスチナ/イスラエル研究会
報告
金城の報告は「記憶」をキーワードに、1970年代から発展してきた研究潮流を整理したうえで、ヌール・マサールハによる「先住民的知識」という視点を軸に、リフター村の出身者による記憶をめぐる活動を分析するものだった。リフター村はエルサレム旧市街の北西方向に広大な土地を有する村だったが、ナクバによって破壊され、現在では55軒の無人化された住居が残されている。報告では村落史の特徴として、①社会関係の土台としての村(親族集団ハムーラなどによる結束)、②村の一体性、③村の持つ重層的な歴史が指摘された。最後にリフターの村民たちが村への帰還実践(訪問)を日常的に行っていることが示され、離散第一世代にとっては苦痛を伴う行為でもあった帰還が、次世代によって知識の保持と共有の取り組みとして継続されていることが明らかにされた。そのうえで、「帰還」が実生活のレベルで取り組まれているリフターの事例は、和平交渉の最終的地位として扱われる難民帰還権の議論に重要な視座を加えるだろうと結んだ。
質疑応答ではリフター村のナクバ以前のパレスチナ社会での位置づけ、「リフターは入り口」という言葉の含意、法廷闘争についての詳細、村落史における女性の扱い、帰属意識の世代間の差違について質問があった。これに対して報告者は、一体性を強調する村落史では社会階層について不問に付す傾向にあること、「入り口」は地理的な意味ではなく祖国パレスチナの解放との関係から理解すべきと推測されること、イスラエル司法での法廷闘争ではリフター村民が「自然保護区」に指定されている点を利用していたこと、数は少ないながら女性による村落史の発表も行われていること、帰還実践においては世代間の差違が確かに観察されることを応答で述べた。
役重の報告はエルサレムのシルワーン村と西岸地区のマサーフェル・ヤッタ地区を事例に、旧約学とパレスチナ問題の連関を論じるものだった。特にパレスチナにおける旧約学/聖書学の系譜をエドワード・ロビンソンによる1838年のシロアム・トンネルの発見から1990年代と2000年代に入ってからのシルワーン村でのイール・ダヴィド基金による活動まで整理し、近年においてはむしろ旧約学/聖書学の発展によって過去の通説が否定される事例もあることが指摘された。また、ヘブロン郊外のマサーフェル・ヤッタ地区では、最高裁の最終的な判定により住民の大量追放の可能性が生じている点に論及があった。特に地区のなかでも規模の大きいアル=トゥワーニー村では、ビザンツ時代の遺構があったことで開発地域の限定や入植者の立ち入りが行われていることが指摘された。そのうえで、イスラエルの入植政策を西側世界が過小評価する認識枠組みの問題に、こうした聖書解釈と連動する歴史認識があるのではないかと問いかけた。
質疑応答では、シルワーンでの住宅壁画の書き手は誰なのか、遺跡の保護・管理主体として国家が機能することはないのか、遺跡の存在を理由に開発差し止めを申し立てることができる主体の範囲(クリスチャンやイスラム教徒は申し立てができないのか)、報告から導かれる結論部と旧約学/聖書学との関係性はどこにあるのか、最高裁の判定が覆った背景とは何かについて質問があった。報告者は、シルワーンの住宅壁画は住民側のアーティストが抵抗の文脈から作成したこと、C地区の特殊性(イスラエルの法律が優越する状況)、聖書に基づいた理解が西側世界の歴史認識をゆがめている可能性、最高裁の最初の判断は追放命令そのものへの判断ではなく暫定的な差し止めであった点を応答で明らかにした。
いずれの報告も聴衆の関心を喚起し、活発な議論が交わされた。
鈴木啓之(東京大学中東地域研究センター)
質疑応答ではリフター村のナクバ以前のパレスチナ社会での位置づけ、「リフターは入り口」という言葉の含意、法廷闘争についての詳細、村落史における女性の扱い、帰属意識の世代間の差違について質問があった。これに対して報告者は、一体性を強調する村落史では社会階層について不問に付す傾向にあること、「入り口」は地理的な意味ではなく祖国パレスチナの解放との関係から理解すべきと推測されること、イスラエル司法での法廷闘争ではリフター村民が「自然保護区」に指定されている点を利用していたこと、数は少ないながら女性による村落史の発表も行われていること、帰還実践においては世代間の差違が確かに観察されることを応答で述べた。
役重の報告はエルサレムのシルワーン村と西岸地区のマサーフェル・ヤッタ地区を事例に、旧約学とパレスチナ問題の連関を論じるものだった。特にパレスチナにおける旧約学/聖書学の系譜をエドワード・ロビンソンによる1838年のシロアム・トンネルの発見から1990年代と2000年代に入ってからのシルワーン村でのイール・ダヴィド基金による活動まで整理し、近年においてはむしろ旧約学/聖書学の発展によって過去の通説が否定される事例もあることが指摘された。また、ヘブロン郊外のマサーフェル・ヤッタ地区では、最高裁の最終的な判定により住民の大量追放の可能性が生じている点に論及があった。特に地区のなかでも規模の大きいアル=トゥワーニー村では、ビザンツ時代の遺構があったことで開発地域の限定や入植者の立ち入りが行われていることが指摘された。そのうえで、イスラエルの入植政策を西側世界が過小評価する認識枠組みの問題に、こうした聖書解釈と連動する歴史認識があるのではないかと問いかけた。
質疑応答では、シルワーンでの住宅壁画の書き手は誰なのか、遺跡の保護・管理主体として国家が機能することはないのか、遺跡の存在を理由に開発差し止めを申し立てることができる主体の範囲(クリスチャンやイスラム教徒は申し立てができないのか)、報告から導かれる結論部と旧約学/聖書学との関係性はどこにあるのか、最高裁の判定が覆った背景とは何かについて質問があった。報告者は、シルワーンの住宅壁画は住民側のアーティストが抵抗の文脈から作成したこと、C地区の特殊性(イスラエルの法律が優越する状況)、聖書に基づいた理解が西側世界の歴史認識をゆがめている可能性、最高裁の最初の判断は追放命令そのものへの判断ではなく暫定的な差し止めであった点を応答で明らかにした。
いずれの報告も聴衆の関心を喚起し、活発な議論が交わされた。
鈴木啓之(東京大学中東地域研究センター)
2022年度の研究会
関西パレスチナ研究会 2022年度第3回研究会
概要:講演は英語で実施されます
Research Seminar by Kansai Society for Palestine Studies
Date and Time Fri. March 24, 3:30pm-7pm (Japan)/8:30am-12pm (Palestine)
Venue Online via Zoom
Registration from HERE
Program
Presentation:
(1) Magid Shihade (Vice President for Academic Affairs at Dar Al Kalima University, Bethlehem)
Settler colonialism in Palestine in a comparative perspective
(2) Kei Saido (Research Student at Graduate School of Human and Environmental Studies, Kyoto University)
Palestinians in Israel and the Future Vision Documents: Searching for a way to binationalism
Commentator: Yoshihiro Yakushige (Adjunct Researcher at the Institute for Study of Humanities and Social Sciences, Doshisha University)
Organized by
Kansai Society for Palestine Studies
Grants-in-Aid for Scientific Research (B) “Formation of New Networks and Liberation Conceptions among Palestinians in the Post-Oslo Era” (Principal Researcher: Taizo Imano)
Co-organized by
Research Group on Palestine/Israel
Contact
palestine.kansai[at]gmail.com ([at]は@に変えてください)
主催:
関西パレスチナ研究会
科研費基盤研究(B)「ポスト・オスロ合意期におけるパレスチナ人の新しいネットワークと解放構想の形成過程」 (研究代表者:今野泰三 課題番号:22H03831)
共催:
パレスチナ/イスラエル研究会
Date and Time Fri. March 24, 3:30pm-7pm (Japan)/8:30am-12pm (Palestine)
Venue Online via Zoom
Registration from HERE
Program
Presentation:
(1) Magid Shihade (Vice President for Academic Affairs at Dar Al Kalima University, Bethlehem)
Settler colonialism in Palestine in a comparative perspective
(2) Kei Saido (Research Student at Graduate School of Human and Environmental Studies, Kyoto University)
Palestinians in Israel and the Future Vision Documents: Searching for a way to binationalism
Commentator: Yoshihiro Yakushige (Adjunct Researcher at the Institute for Study of Humanities and Social Sciences, Doshisha University)
Organized by
Kansai Society for Palestine Studies
Grants-in-Aid for Scientific Research (B) “Formation of New Networks and Liberation Conceptions among Palestinians in the Post-Oslo Era” (Principal Researcher: Taizo Imano)
Co-organized by
Research Group on Palestine/Israel
Contact
palestine.kansai[at]gmail.com ([at]は@に変えてください)
主催:
関西パレスチナ研究会
科研費基盤研究(B)「ポスト・オスロ合意期におけるパレスチナ人の新しいネットワークと解放構想の形成過程」 (研究代表者:今野泰三 課題番号:22H03831)
共催:
パレスチナ/イスラエル研究会
報告
「パレスチナ/イスラエル紛争の変容」 2022年度第4回研究会
概要
テーマ 変化の諸相
日時 2023年2月6日(月)15:00–19:00
場所 本郷サテライト5階セミナールーム,オンライン会議室
15:00-15:50 細田和江(AA研共同研究員・東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所)
「イスラエルのパレスチナ人作家と翻訳」
16:00-16:50 浜中新吾(AA研共同研究員・龍谷大学)
「イスラエル社会の分断、政策選好、および民主主義の後退」
17:00-17:40 全体討議
18:00- 研究メンバー会議(事務連絡等)
Zoomによるオンライン参加登録はこちら
会場での参加はこちら
主催:東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所共同利用・共同研究課題「パレスチナ/イスラエル紛争の変容」(2022~24年度)
パレスチナ/イスラエル研究会
日時 2023年2月6日(月)15:00–19:00
場所 本郷サテライト5階セミナールーム,オンライン会議室
15:00-15:50 細田和江(AA研共同研究員・東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所)
「イスラエルのパレスチナ人作家と翻訳」
16:00-16:50 浜中新吾(AA研共同研究員・龍谷大学)
「イスラエル社会の分断、政策選好、および民主主義の後退」
17:00-17:40 全体討議
18:00- 研究メンバー会議(事務連絡等)
Zoomによるオンライン参加登録はこちら
会場での参加はこちら
主催:東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所共同利用・共同研究課題「パレスチナ/イスラエル紛争の変容」(2022~24年度)
パレスチナ/イスラエル研究会
報告
細田和江氏(AA研共同研究員・東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所)は、イスラエルにおけるミズラヒームやパレスチナ・アラブ人の文学活動について報告し、特にアラビア語による執筆の拡大とヘブライ語への翻訳の増加というここ10年の動向を論じた。
近年、ヘブライ文学に代わってイスラエル文学という枠組みが受け入れられることで、イスラエルでアラブ文学の翻訳が流通するようになり、パレスチナ・アラブ人がヘブライ語ではなく母語で執筆した作品が翻訳によって書店に並ぶようになった。アラビア語の作品をヘブライ語に自己翻訳する事例やアラビア語とヘブライ語を組み合わせて創作する試みもあり、これらの動向はイスラエル文化の脱シオニズム化と並行するものとして捉えられる。
質疑応答では文学の動向とイスラエル社会の変化の関係性、読み手の層や社会の需要に関する議論がなされた。
浜中新吾氏(AA研共同研究員・龍谷大学)は、イスラエルにおける近年のエスノナショナルな政治の傾向と民主主義の機能不全について、有権者の政策選好を分析することでその原因を論じた。
同氏は2022年9月14日から10月2日にかけて、ユダヤ人有権者の政策選好を把握するためのコンジョイント実験をウェブ上で行った。その結果、親ネタニヤフ派の有権者は反民主的・民族的な政策選好を持っていることが改めて確認できた。また、イスラエルでは民主主義国家とユダヤ人国家という基本的なヴィジョンをめぐって深刻な二極化が起きており、ユダヤ人有権者はユダヤ人国家を目指す方向に傾いていることがデータ上で明らかになった。ただし、本調査の回答者にはアラブ系市民が含まれておらず、実験を用いていない他の実証研究では電話や対面調査によってアラブ系市民にアプローチしている。
質疑応答ではアイデンティティ投票やイスラエル政治の権威主義的な傾向について議論がなされた。
溝川貴己(早稲田大学文学部中東・イスラーム研究コース)
近年、ヘブライ文学に代わってイスラエル文学という枠組みが受け入れられることで、イスラエルでアラブ文学の翻訳が流通するようになり、パレスチナ・アラブ人がヘブライ語ではなく母語で執筆した作品が翻訳によって書店に並ぶようになった。アラビア語の作品をヘブライ語に自己翻訳する事例やアラビア語とヘブライ語を組み合わせて創作する試みもあり、これらの動向はイスラエル文化の脱シオニズム化と並行するものとして捉えられる。
質疑応答では文学の動向とイスラエル社会の変化の関係性、読み手の層や社会の需要に関する議論がなされた。
浜中新吾氏(AA研共同研究員・龍谷大学)は、イスラエルにおける近年のエスノナショナルな政治の傾向と民主主義の機能不全について、有権者の政策選好を分析することでその原因を論じた。
同氏は2022年9月14日から10月2日にかけて、ユダヤ人有権者の政策選好を把握するためのコンジョイント実験をウェブ上で行った。その結果、親ネタニヤフ派の有権者は反民主的・民族的な政策選好を持っていることが改めて確認できた。また、イスラエルでは民主主義国家とユダヤ人国家という基本的なヴィジョンをめぐって深刻な二極化が起きており、ユダヤ人有権者はユダヤ人国家を目指す方向に傾いていることがデータ上で明らかになった。ただし、本調査の回答者にはアラブ系市民が含まれておらず、実験を用いていない他の実証研究では電話や対面調査によってアラブ系市民にアプローチしている。
質疑応答ではアイデンティティ投票やイスラエル政治の権威主義的な傾向について議論がなされた。
溝川貴己(早稲田大学文学部中東・イスラーム研究コース)
「パレスチナ/イスラエル紛争の変容」 2022年度第3回研究会
概要
テーマ 枠組みの再検討
日時 2023年1月20日(金)14:00–19:00
場所 本郷サテライト5階セミナールーム,オンライン会議室
14:00–14:50 錦田愛子(AA研共同研究員,慶應義塾大学)
「オスロ合意による体制構築の課題:主権と治安管理をめぐるトレードオフ」
15:00–15:50 山本健介(AA研共同研究員,静岡県立大学)
「オスロ合意と『イスラエルのイスラーム運動』:国家との関係と民族意識」(仮)
16:00–16:50 鶴見太郎(AA研共同研究員,東京大学)
「シオニスト/イスラエルの対アラブ観の変遷」
17:00–17:40 全体討議
18:00– 研究メンバー会議(事務連絡等)
Zoomによるオンライン参加登録はこちら
会場での参加はこちら
主催:東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所共同利用・共同研究課題「パレスチナ/イスラエル紛争の変容」(2022~24年度)
パレスチナ/イスラエル研究会
日時 2023年1月20日(金)14:00–19:00
場所 本郷サテライト5階セミナールーム,オンライン会議室
14:00–14:50 錦田愛子(AA研共同研究員,慶應義塾大学)
「オスロ合意による体制構築の課題:主権と治安管理をめぐるトレードオフ」
15:00–15:50 山本健介(AA研共同研究員,静岡県立大学)
「オスロ合意と『イスラエルのイスラーム運動』:国家との関係と民族意識」(仮)
16:00–16:50 鶴見太郎(AA研共同研究員,東京大学)
「シオニスト/イスラエルの対アラブ観の変遷」
17:00–17:40 全体討議
18:00– 研究メンバー会議(事務連絡等)
Zoomによるオンライン参加登録はこちら
会場での参加はこちら
主催:東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所共同利用・共同研究課題「パレスチナ/イスラエル紛争の変容」(2022~24年度)
パレスチナ/イスラエル研究会
報告
錦田報告では、オスロ合意によってもたらされた枠組みがパレスチナ問題に置いてどのような影響を及ぼしたのかについて発表された。はじめに、イスラエルパレスチナ紛争におけるオスロ合意の意義と残された課題について明示したうえで、オスロ合意が生み出した新たな問題には、パレスチナの主権の制限が厳しくなったことにくわえて、自治政府の役割がイスラエルの下部組織へと変化してしまったことを挙げた。
山本報告では、オスロ合意で残された課題とイスラーム運動の位置づけが取り上げられた。はじめに、オスロ合意に対する48年パレスチナ人の期待観と要求について示したうえで、ナクサ以降の宗教復興からイスラーム運動が形成され、その目標について明示した。クネセト選挙以降にイスラーム運動は「南部潮流」と「北部潮流」に分岐していく過程を踏まえて、パレスチナ人の民族意識が、イスラエルの政治的、社会的制度とは離れてしまっていると示した。
鶴見報告では、シオニストがどのようにアラブを捉え、対峙していたのかについて、個人に焦点をあてて分析がなされた。初めに、アラブ観の主な要素には、「危険」「憧れ」「変化」といった三つの要素を説明し、対アラブ観についての話では、アラブ人とどのように対峙するかについては、イスラエル内外のアラブ人を分けて対応する立場、アラブ人を域外に移送しようとする立場、アラブ人と二民族国家をつくろうとする立場をそれぞれ出しながら、シオニストの政治、宗教、人口構成という事情を踏まえて説明した。
いずれの報告もオスロ合意による法制度や認識の変化を扱い、活発な質疑応答が行われた。
中本美羽(日本女子大学・文学部史学科)
山本報告では、オスロ合意で残された課題とイスラーム運動の位置づけが取り上げられた。はじめに、オスロ合意に対する48年パレスチナ人の期待観と要求について示したうえで、ナクサ以降の宗教復興からイスラーム運動が形成され、その目標について明示した。クネセト選挙以降にイスラーム運動は「南部潮流」と「北部潮流」に分岐していく過程を踏まえて、パレスチナ人の民族意識が、イスラエルの政治的、社会的制度とは離れてしまっていると示した。
鶴見報告では、シオニストがどのようにアラブを捉え、対峙していたのかについて、個人に焦点をあてて分析がなされた。初めに、アラブ観の主な要素には、「危険」「憧れ」「変化」といった三つの要素を説明し、対アラブ観についての話では、アラブ人とどのように対峙するかについては、イスラエル内外のアラブ人を分けて対応する立場、アラブ人を域外に移送しようとする立場、アラブ人と二民族国家をつくろうとする立場をそれぞれ出しながら、シオニストの政治、宗教、人口構成という事情を踏まえて説明した。
いずれの報告もオスロ合意による法制度や認識の変化を扱い、活発な質疑応答が行われた。
中本美羽(日本女子大学・文学部史学科)
関西パレスチナ研究会 2022年度第2回研究会
概要
日時 2023年1月14日(土)13:00–17:30
場所 大阪女学院大学2階演習室
13:00~13:20 挨拶・自己紹介
13:20~14:20 研究報告 役重善洋氏(同志社大学人文科学研究所嘱託研究員)
「シオニズムと聖書考古学~エルサレムおよびマサーフェルヤッタを訪ねて」
(休憩10分)
14:30~15:30 会議参加報告 金城美幸氏(立命館大学生存学研究センタープロジェクト研究員)
「Kairos PalestineおよびGlobal Kairos for Justice国際会議に参加して」
15:30~15:45 コメント 今野泰三氏(中京大学准教授)
15:45~16:45 質疑応答
16:45~17:15 関西パレスチナ研究会運営会議
申し込みフォーム
主催:関西パレスチナ研究会 palestine.kansai[at]gmail.com ([at]は@に変えてください)
(研究会ブログ:http://kansai-palestinestudies.blogspot.jp/)
共催:科研費基盤研究(B)「ポスト・オスロ合意期におけるパレスチナ人の新しいネットワークと解放構想の形成過程」 (研究代表者:今野泰三 課題番号:22H03831)
パレスチナ/イスラエル研究会
場所 大阪女学院大学2階演習室
13:00~13:20 挨拶・自己紹介
13:20~14:20 研究報告 役重善洋氏(同志社大学人文科学研究所嘱託研究員)
「シオニズムと聖書考古学~エルサレムおよびマサーフェルヤッタを訪ねて」
(休憩10分)
14:30~15:30 会議参加報告 金城美幸氏(立命館大学生存学研究センタープロジェクト研究員)
「Kairos PalestineおよびGlobal Kairos for Justice国際会議に参加して」
15:30~15:45 コメント 今野泰三氏(中京大学准教授)
15:45~16:45 質疑応答
16:45~17:15 関西パレスチナ研究会運営会議
申し込みフォーム
主催:関西パレスチナ研究会 palestine.kansai[at]gmail.com ([at]は@に変えてください)
(研究会ブログ:http://kansai-palestinestudies.blogspot.jp/)
共催:科研費基盤研究(B)「ポスト・オスロ合意期におけるパレスチナ人の新しいネットワークと解放構想の形成過程」 (研究代表者:今野泰三 課題番号:22H03831)
パレスチナ/イスラエル研究会
報告
「パレスチナ/イスラエル紛争の変容」 2022年度第2回研究会
概要
テーマ 最終的地位の現在
日時 2022年10月15日(土)14:00–19:00
場所 本郷サテライト,オンライン会議室
14:00–14:50 今野泰三(AA研共同研究員・中京大学)
「ポスト・オスロ合意期における植民地主義研究の再評価と進展」
15:00–15:50 南部真喜子(AA研共同研究員・東京外国語大学)
「エルサレムにおけるオスロ合意後の市民権と生活空間」
16:00–16:50 児玉恵美(AA研共同研究員・東京外国語大学)
「レバノンにおけるパレスチナ難民帰還権への意識」
17:00–17:40 全体討議
18:00– 研究メンバー会議(事務連絡等)
Zoomによるオンライン参加登録はこちら
会場での参加はこちら
主催:東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所共同利用・共同研究課題「パレスチナ/イスラエル紛争の変容」(2022~24年度)
パレスチナ/イスラエル研究会
日時 2022年10月15日(土)14:00–19:00
場所 本郷サテライト,オンライン会議室
14:00–14:50 今野泰三(AA研共同研究員・中京大学)
「ポスト・オスロ合意期における植民地主義研究の再評価と進展」
15:00–15:50 南部真喜子(AA研共同研究員・東京外国語大学)
「エルサレムにおけるオスロ合意後の市民権と生活空間」
16:00–16:50 児玉恵美(AA研共同研究員・東京外国語大学)
「レバノンにおけるパレスチナ難民帰還権への意識」
17:00–17:40 全体討議
18:00– 研究メンバー会議(事務連絡等)
Zoomによるオンライン参加登録はこちら
会場での参加はこちら
主催:東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所共同利用・共同研究課題「パレスチナ/イスラエル紛争の変容」(2022~24年度)
パレスチナ/イスラエル研究会
報告
今野泰三氏(AA研共同研究員・中京大学)の報告では、パレスチナ/イスラエル研究における植民地主義と入植者植民地主義の概念及び分析枠組みの意義と課題を論じることが目的とされた。はじめに、パレスチナ人の入植地問題と植民地主義概念を論じた先行研究の内容と課題を整理し、入植者植民地主義概念の意義が、パレスチナ人が行ってきた反植民地主義研究と帝国主義論から展開してきた植民地主義研究を架橋するところにあると述べた。次に、同概念の幾つかの課題を示した上で、被植民者を対象とした様々なレベルからの分析が必要だと指摘した。最後に、ベドウィンを対象とする報告者の今後の研究方針が示された。
質疑応答では、入植者植民地主義の位置付け、ジェンダーの視点、ベドウィンに着目する意義などの議論が提起された。
児玉恵美氏(AA研共同研究員・東京外国語大学)の報告では、レバノン国内のパレスチナ難民の境遇を、シャーティーラー難民キャンプの変容から論じることが目的とされた。その中で、先行研究を整理した上で、現地調査におけるパレスチナ難民の語りから見えてきた難民キャンプへの愛着、殉難者墓地に対するパレスチナ難民の認識・利用のあり方から、同キャンプにおける政治的暴力が持続していることを指摘した。
質疑応答では、聞き取りの対象者の選定方法、殉難者墓地の存続する背景やパレスチナ難民への働きかけ、死者の語りのあり方などが活発に議論された。
浪内紫雲(東京外国語大学大学院修士課程)
質疑応答では、入植者植民地主義の位置付け、ジェンダーの視点、ベドウィンに着目する意義などの議論が提起された。
児玉恵美氏(AA研共同研究員・東京外国語大学)の報告では、レバノン国内のパレスチナ難民の境遇を、シャーティーラー難民キャンプの変容から論じることが目的とされた。その中で、先行研究を整理した上で、現地調査におけるパレスチナ難民の語りから見えてきた難民キャンプへの愛着、殉難者墓地に対するパレスチナ難民の認識・利用のあり方から、同キャンプにおける政治的暴力が持続していることを指摘した。
質疑応答では、聞き取りの対象者の選定方法、殉難者墓地の存続する背景やパレスチナ難民への働きかけ、死者の語りのあり方などが活発に議論された。
浪内紫雲(東京外国語大学大学院修士課程)
「パレスチナ/イスラエル紛争の変容」 2022年度第1回研究会
概要
テーマ 問い直されるオスロ合意の前提
日時 2022年8月5日(金)14:00–19:00
場所 本郷サテライト,オンライン会議室
14:00–14:50 鈴木啓之(AA研共同研究員・東京大学)
「30年を迎えるオスロ体制と諸研究の課題」
15:00–15:50 江﨑智絵(AA研共同研究員・防衛大学校)
「中東国際関係にみるオスロ合意以降の変容」
16:00–16:50 田浪亜央江(AA研共同研究員・広島市立大学)
「抵抗と平和構築のあいだ オスロ合意後のパレスチナの演劇活動への視点」
17:00–17:40 全体討議
18:00– 研究メンバー会議(事務連絡等)
主催:東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所共同利用・共同研究課題「パレスチナ/イスラエル紛争の変容」(2022~24年度)
パレスチナ/イスラエル研究会
日時 2022年8月5日(金)14:00–19:00
場所 本郷サテライト,オンライン会議室
14:00–14:50 鈴木啓之(AA研共同研究員・東京大学)
「30年を迎えるオスロ体制と諸研究の課題」
15:00–15:50 江﨑智絵(AA研共同研究員・防衛大学校)
「中東国際関係にみるオスロ合意以降の変容」
16:00–16:50 田浪亜央江(AA研共同研究員・広島市立大学)
「抵抗と平和構築のあいだ オスロ合意後のパレスチナの演劇活動への視点」
17:00–17:40 全体討議
18:00– 研究メンバー会議(事務連絡等)
主催:東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所共同利用・共同研究課題「パレスチナ/イスラエル紛争の変容」(2022~24年度)
パレスチナ/イスラエル研究会
報告
鈴木啓之氏(AA研共同研究員・東京大学)の報告では、はじめにオスロ合意とオスロ体制を研究する目的が説明され、オスロ合意がパレスチナ問題の研究動向の転換点であり、一つの時代区分としての役割を担っている点、またオスロ・プロセスが批判対象となっている点が研究対象としての重要性を際立たせていると指摘がなされた。また、オスロ・プロセス、オスロ体制についての研究の動向と課題点、委任統治期研究をはじめ広範な分野からのパレスチナ/イスラエル研究の現状が示された。
質疑応答では、オスロ体制という言葉が示す意味合い、変容する主体と研究者の視点の変化の認識について議論が提起された。
江﨑智絵氏(AA研共同研究員・防衛大学校)の報告は、国際関係論的視点からオスロ体制に関わるアクターや国家間関係の変容を問い直すことを目的とした。オスロ体制は国家主体中心の地域的安全保障体制であり、外的要因や中東諸国の内部変化からの影響により変容してきたことが示された。非国家主体の重要性、超国家的な共同体意識とその担い手を考察したうえで、新たな地域的安全保障体制の構築を必要とするイスラエルとアラブ諸国との関係正常化が進んでいるという指摘がなされた。
質疑応答では、ネゲブ・フォーラムの実効性、地域安全保障における非国家主体の位置付けについて等活発な議論が交わされた。
田浪亜央江氏(AA研共同研究員・広島市立大学)の報告では、パレスチナにおける演劇活動の視点から、オスロ体制が形成したパレスチナ社会に対する考察が行われた。占領に対する抵抗に加え、国際社会が規定する平和構築への抵抗を示す表現や演劇関係者の発言に注目するという視点が示された。また、パレスチナの社会内部のマイノリティの抑圧を映し出す演劇は、パレスチナの大衆的な支持を得ているわけではないとも指摘された。
質疑応答では、インティファーダを経験した世代と現在の若年層の世代間のギャップやパレスチナ社会のユースムーブメントと演劇の関連性について幅広い視点からの議論が行われた。
虎熊 歩(早稲田大学大学院修士課程)
質疑応答では、オスロ体制という言葉が示す意味合い、変容する主体と研究者の視点の変化の認識について議論が提起された。
江﨑智絵氏(AA研共同研究員・防衛大学校)の報告は、国際関係論的視点からオスロ体制に関わるアクターや国家間関係の変容を問い直すことを目的とした。オスロ体制は国家主体中心の地域的安全保障体制であり、外的要因や中東諸国の内部変化からの影響により変容してきたことが示された。非国家主体の重要性、超国家的な共同体意識とその担い手を考察したうえで、新たな地域的安全保障体制の構築を必要とするイスラエルとアラブ諸国との関係正常化が進んでいるという指摘がなされた。
質疑応答では、ネゲブ・フォーラムの実効性、地域安全保障における非国家主体の位置付けについて等活発な議論が交わされた。
田浪亜央江氏(AA研共同研究員・広島市立大学)の報告では、パレスチナにおける演劇活動の視点から、オスロ体制が形成したパレスチナ社会に対する考察が行われた。占領に対する抵抗に加え、国際社会が規定する平和構築への抵抗を示す表現や演劇関係者の発言に注目するという視点が示された。また、パレスチナの社会内部のマイノリティの抑圧を映し出す演劇は、パレスチナの大衆的な支持を得ているわけではないとも指摘された。
質疑応答では、インティファーダを経験した世代と現在の若年層の世代間のギャップやパレスチナ社会のユースムーブメントと演劇の関連性について幅広い視点からの議論が行われた。
虎熊 歩(早稲田大学大学院修士課程)
関西パレスチナ研究会 2022年度第1回研究会
概要
関西パレスチナ研究会の2022年度第1回研究会では、今年2月にご著書The Fragmentation of Palestine: Identity and Isolation since the Second Intifada. (Tauris Academic Studies)を刊行されたジョシュア・リカードさんに、パレスチナのヨルダン川西岸地区北部の都市ナーブルスを中心としたパレスチナ人コミュニティにおける社会的分断についてご報告いただきます。
著書紹介:https://www.bloomsbury.com/uk/fragmentation-of-palestine-9781784535872/
多くの皆様のご参加をお待ちしています。
日時:2022年5月28日(土)14:00~17:30
形式:対面とオンライン(Zoom)のハイブリッド開催
場所:大阪女学院大学2階演習室
プログラム(予定)
14:00~14:20 挨拶・自己紹介
14:20~16:20(報告60分+討論60分)
*英語にて行われます(通訳なし)
発表者:ジョシュア・リカード氏(Dr. Joshua Rickard)(熊本大学多言語文化総合教育センター特任准教授)
タイトル:Social Fragmentation and Changes in Community Organization in the Post-Oslo Era
発表要旨:This talk will focus on social fragmentation in Palestinian communities that has developed through various levels of isolation, and the ways that communities have adapted in response. Increased political and class divisions since the Oslo process, as well as frequently changing restrictions, have resulted in changes in how communities relate to each other, contributing to the extraordinarily personal experience of uncertainty in everyday life. With a focus especially on the Nablus region I will discuss changes in community formations and expressions of identity over time, and the possibility for a reformation of social organization which transcends traditional political discourse.
コメンテーター:髙橋宗瑠氏(大阪女学院大学教授)
(休憩10分)
16:30~17:30 関西パレスチナ研究会運営会議
■参加申し込み方法
参加ご希望の方は、開催前日までに下記のフォームに記入の上、送信してください。(オンライン参加の方には開催前にZoomリンクをお送りします)
https://forms.gle/M2nm5XA6RciVoogm6
■主催:関西パレスチナ研究会 palestine.kansai[at]gmail.com ([at]は@に変えてください)
(研究会ブログ:http://kansai-palestinestudies.blogspot.jp/)
■共催:科研費基盤研究(B)「ポスト・オスロ合意期におけるパレスチナ人の新しいネットワークと解放構想の形成過程」 (研究代表者:今野泰三 課題番号:22H03831)
著書紹介:https://www.bloomsbury.com/uk/fragmentation-of-palestine-9781784535872/
多くの皆様のご参加をお待ちしています。
日時:2022年5月28日(土)14:00~17:30
形式:対面とオンライン(Zoom)のハイブリッド開催
場所:大阪女学院大学2階演習室
プログラム(予定)
14:00~14:20 挨拶・自己紹介
14:20~16:20(報告60分+討論60分)
*英語にて行われます(通訳なし)
発表者:ジョシュア・リカード氏(Dr. Joshua Rickard)(熊本大学多言語文化総合教育センター特任准教授)
タイトル:Social Fragmentation and Changes in Community Organization in the Post-Oslo Era
発表要旨:This talk will focus on social fragmentation in Palestinian communities that has developed through various levels of isolation, and the ways that communities have adapted in response. Increased political and class divisions since the Oslo process, as well as frequently changing restrictions, have resulted in changes in how communities relate to each other, contributing to the extraordinarily personal experience of uncertainty in everyday life. With a focus especially on the Nablus region I will discuss changes in community formations and expressions of identity over time, and the possibility for a reformation of social organization which transcends traditional political discourse.
コメンテーター:髙橋宗瑠氏(大阪女学院大学教授)
(休憩10分)
16:30~17:30 関西パレスチナ研究会運営会議
■参加申し込み方法
参加ご希望の方は、開催前日までに下記のフォームに記入の上、送信してください。(オンライン参加の方には開催前にZoomリンクをお送りします)
https://forms.gle/M2nm5XA6RciVoogm6
■主催:関西パレスチナ研究会 palestine.kansai[at]gmail.com ([at]は@に変えてください)
(研究会ブログ:http://kansai-palestinestudies.blogspot.jp/)
■共催:科研費基盤研究(B)「ポスト・オスロ合意期におけるパレスチナ人の新しいネットワークと解放構想の形成過程」 (研究代表者:今野泰三 課題番号:22H03831)