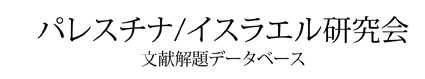Facts on the Ground
本書はミシェル・フーコー、エドワード・サイードらによる制度としての学問の対象化の作業、および「学問の客観性」こそが極めてヨーロッパ中心主義的であるとの提起をふまえ、パレスチナ/イスラエルにおける考古学を対象とした(ポスト)コロニアル研究である。19世紀後半、英国の軍事的要請を背景としつつ聖書研究を目的に設立された「パレスチナ探査基金」による「植民地における学問研究」をたどることから始まり、委任統治期のパレスチナにおけるユダヤ人考古学者らによる「ユダヤ・パレスチナ探査協会」の活動を明らかにしてゆく。協会が科学的作業を指向する一方で、一般の入植者が「国土を知る」ことを目指しハイキングを通じた教育啓蒙活動を広めたことなど、のちに考古学が「国民的趣味」となった背景が描かれている。個々の考古学者の見解の違いや対立が、むしろ大枠で「パレスチナにおけるユダヤ民族の一貫した存在」という歴史像を造り出してゆくプロセスの描写はひじょうに丁寧であり、多くの先行研究に依拠しながら筆者の立場をそこから一歩越えた問いとして明示化しようとする姿勢がつねに存在する。
第三次中東戦争のさなかでのエルサレム旧市街のムスリム地区の破壊、その後現在まで続くユダヤ地区の再開発、全体としての「ユダヤ化」の経緯については、とかくイスラエルによる「歴史のねつ造」と形容されがちであるが、むしろ学問としての考古学の「客観性」、科学的方法論の厳密さを追求する姿勢のなかでこうした「歴史破壊」が生まれてきたという指摘(だからこそ「学問」そのものが問われる必要がある)は重要である。(田浪)