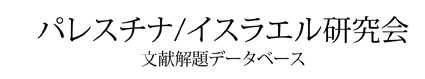No Way Out: The Politics of Polish Jewry 1935–1939
両大戦間期のポーランドはヨーロッパで第一、世界で第二の規模のユダヤ人口を擁した(第一は米国)。そこでのユダヤ人の経験は、戦後のシオニズム運動とイデオロギーを大きく規定したといっても過言でない。本書が扱うのは、大戦前夜に猖獗をきわめたポーランドの反ユダヤ主義と、それにたいするユダヤ緒政党の反応である。
本書が焦点を当てるのは、唯一強大な政治的指導力を発揮したユゼフ・ピウスツキの死去(1935年)から1939年の開戦までである。もともと社会主義者で反ユダヤ主義に対して抑制的な態度をとっていたピウスツキの死は、従来反ユダヤ主義色の強かった右派のライバル政党、国民(民主)党(エンデツィア)が力を強める契機を与えた。他方、隣国ドイツでナチスが台頭すると、反ユダヤ主義はポーランドの右派政党や青年組織によって公然と唱道されるようになり、ポーランドの社会不安――とりわけ世界恐慌以降の経済危機――の要因をすべてユダヤ人に転化するような言説が流布した。本書は、ピウスツキの時代(サナチア体制)と1935年以降のポーランドの政治的状況を概観したのち[第1章・第2章]、ユダヤ人に対する経済的ボイコット[第3章]、反ユダヤ暴力/暴動[第4章]、「ゲットー席」の設置など大学・高等教育機関における迫害[第5章]、コシェル(清浄肉)禁止法などの反ユダヤ法[第6章]、という4点から、この時期の反ユダヤ主義の事例を詳細に論ずる。これらの状況は、ポーランド国内の他のマイノリティ(ウクライナ人、ドイツ人)とユダヤ人の関係にも影響を与え、ユダヤ人は非ポーランド人の間でもますます孤立していった[第8章]。エスニック・ナショナリズムの要請からユダヤ人の移民を推進するポーランド政府と、迫害と窮乏化からの脱出口を移民に求めるシオニストとの間にある種の協力関係が生まれる一方、双方の思惑は英委任統治領パレスチナを含む諸外国の移民制限によって挫折を余儀なくされる[第9章]。
一連の状況に対するユダヤ政党(一般シオニスト、ブンド、正統派=アグダト・イスラエル、フォルキスト)の反応は、各章で指導者の言動をもとにつぶさに描き出されている。本書の随所では、ポーランド・ユダヤ社会が政治イデオロギーごとの分裂を克服できず、指導者の不在から共通の危機に対処しえなかったことが指摘されている。1938年〜39年にかけて、ポーランド・ユダヤ社会は、従来多くの支持を集めていた正統派とシオニストが、それぞれ政治的無力と移民制限によって信頼を失墜し、それに対して、反ユダヤ主義への抵抗を唯一可視的に示せたブンドが支持を集めるという、政治的布置の大きな転換を経験した。だが、このとき大衆的支持を得たブンドは、皮肉にも、階級政党としての立場にこだわり、他のユダヤ人政党との協力を拒む頑さにおいてもっとも顕著な政党でもあった。かくして、ポーランド・ユダヤ社会は、統一的な抵抗体制を整えられないまま、最後の時期へと突入していく[第10章]。
日本では、ナチズムとホロコーストのインパクトから、反ユダヤ主義といえばまずドイツという印象が強く、ポーランドの反ユダヤ主義はその影に隠れがちだといえるだろう。だが、本書を紐解けば、ユダヤ人の大量虐殺という現象がまだ予兆もされなかった時期に、マイノリティとしてのユダヤ人がマジョリティ社会からいかに出口なきまで追いつめられ(No way out)、生存を脅かされていたかを、手に取るように理解することができる。このことは、シオニズムのイデオロギーが現在においてなおかくも「反ユダヤ主義」の脅威に突き動かされているのかを理解する一助にもなりうるかもしれない。
なお、本書の射程は1935年から1939年と短期間だが、その分きわめて詳細な叙述スタイルをとっており、入門書というより専門書の趣が強い。戦間期ポーランドのユダヤ社会を俯瞰しようと思えば、Ezra Mendelson, The Jews of East Central Europe between the World Wars (Bloomington, Indiana Univ. Press 1983) の第一章 “Poland” がコンパクトさ、過不足のなさから最適である。(西村木綿)